-
「夏は昆布とウニ、冬は“昆布の旅”へ
─礼文島の海とともに生きる石原さんの1年─」

北海道にある礼文島で漁師として活躍する石原さんですが、現在やられている漁師の仕事について教えてください。
僕がやっている漁師の仕事は、季節によって内容が変わり、夏のメインは昆布とウニの漁です。礼文島では小さな船に乗って、海の中をのぞく ガラス箱という道具を使いながら、棒の先に鉾や網をつけてウニを取ります。昆布は、長い鎌のような道具を使って海から切り取り、陸に上げたら “完全天日干し”という方法で、太陽と潮風だけでじっくり乾かします。このやり方は手間も時間もかかりますが、僕はこの方法にこだわっています。
秋から冬は、ナマコやアワビ、タコなどの磯物を取ります。それ以外にも、冬は親方の大きな船で沖に出て、タラを取る漁の手伝いをすることもあります。1年を通して見ると、夏に集中して稼ぎ、冬は取れるものが少ないのが礼文島の漁の特徴です。
そのため、現在では、夏は礼文島で漁をして、冬は全国の人たちに自分の採った昆布を直接届ける“昆布の旅”ということをしています。
-
「自転車で日本一周の夢が導いた礼文島での人生」
石原さんは、旭川の出身ということですが礼文島との出会いはなんだったのでしょうか。
もともと僕は、北海道の旭川市にある障がい者施設で介護士として働いていました。仕事はやりがいもあって楽しかったのですが、「このまま同じ仕事だけで人生が終わってしまっていいのかな」と悩むようになり、本当にやりたいことを考えたときに浮かんだのが、「自転車で日本一周」という夢でした。
その旅の資金を貯めるために、偶然見つけたのが礼文島でのアルバイトでした。そんな礼文島との出会いから、実際に島で暮らしてみると、大自然の景色に感動して、島の魅力にすっかり惹かれました。そして、自転車旅を終えたあと、「もう一度、礼文島に行って、次は住んでみよう」、そんな想いから僕は礼文島に移住することになりました。
-
「海とともに生きる姿に惹かれて
─暮らして見えてきた“漁師としての道”─」

礼文島に住んでからは、すぐに漁師になることは決めていたのでしょうか。
礼文島に移住した当初は、工事現場の日雇いの仕事をしていました。最初は、漁師になりたくて礼文島に来たわけではなく、「とにかく礼文島に住むこと」を考えての移住でした。
しかし、礼文島はまさに“漁師の町”。当時の人口はわずか3,000人ほどでしたが、農家も酪農家も一軒もなく、ほとんどの人が漁業に関わっている島でした。そんな環境で暮らしていると、仕事の合間にふと目に入ってくるのは、海に出てウニや昆布を採る漁師たちの姿でした。波をかきわけて進む船や、黙々と網を引く背中、その姿を毎日のように見ているうちに、「漁師ってかっこいいな」と、漁師への憧れが強くなっていきました。
-
「3年越しの一歩
─石原さんの漁師人生のはじまり─」

“漁師”という仕事に憧れてから、石原さんが漁師になるまでの道のりを教えてください。
漁師に憧れを持ったとはいえ、身近な人に漁業をしている親戚もいない自分にとって、その道は遠く感じられました。「なってみたい。でも、どうすれば漁師になれるのかわからない」そんなもどかしい気持ちを抱えたまま、3年ほどが過ぎていきました。
転機が訪れたのは、そんなある日のことでした。近所の漁師家族が、「仕事を手伝ってくれる人を探している。手伝ってくれたら、漁業のことを教える。」そう言って従業員として迎え入れてくれたことが、私の漁師人生の始まりでした。こうして、師匠と呼べる存在と出会えたことで、礼文島に移住して3年目、ようやく「漁師としての一歩」を踏み出すことができたのです。
-
「船・道具・免許…漁師に必要な準備とは?」
この記事を読んでいる学生に漁師になるために必要な準備などを教えてください。
漁師になるまでの道のりにはいくつかの方法がありますが、多くの人にとって、最初のステップは「漁を教えてくれる親方(師匠)を見つけること」です。ほとんどの地域では、いきなり一人前の漁師になれるわけではなく、まずは親方のもとで1〜2年ほど修業しながら、漁のやり方や道具の扱いを学んでいきます。
また、漁師になるには、農家が農協に所属するのと同じように、「漁業協同組合(漁協)」への加入が必要です。漁業協同組合に入ることで、使える漁場や地域のルールが定まります。
さらに、漁業権を取得することも重要なステップです。これは、漁業協同組合が管理する海でウニや昆布などを採るための許可で、地域によって費用や手続きが異なります。
また、漁師として独立するには、道具や設備も一通りそろえなければなりません。ウニや昆布を採るためのガラス箱、鉾(ほこ)、網、鎌といった道具、昆布を干すスペースや作業場など、多くの準備が必要です。
そして、その船を運転するために必要な、小型船舶免許が必要です。このように、漁師になるにはさまざまなハードルがありますが、ひとつひとつのステップを丁寧に踏んでいくことで、地域に根ざした働き方ができるようになります。
-
「海と人をつなぐ“昆布の旅”、
石原さんの新しい挑戦」

冒頭におっしゃっていた“昆布の旅”についても教えてください。
“昆布の旅”というのは、僕が家族と一緒にやっている、自分で取った昆布を全国のお客さんに直接届ける活動のことです。僕たちは、これを“昆布の旅”と呼んでいます。僕は、太陽と潮風だけで仕上げる“完全天日干し”という昔ながらの方法にこだわっています。この方法で作った昆布は、香りもよくて、出汁もたっぷり出ます。手間はかかりますが、自分が本当においしいと思う昆布を作りたいので、この方法を大事にしています。
しかし、私たちの地域では、漁師が取った昆布は通常、漁業協同組合に出荷します。そうすることで、安定した収入が得られたり販売の手間が省けたりするメリットがありますが、どんなに手間ひまをかけてこだわった昆布でも、ほかの昆布と全部同じ扱いになってしまい、自分の昆布ならではの価値をお客さんに伝えられません。
そこで思いついたのが、自分で昆布を直接届けることでした。冬の間、昆布を車に積んで、家族で日本中を回り、料理人や一般のお客さんに昆布を手渡しで販売します。直接届けると、「美味しかった」「また買いたい」という感想がその場で聞けるし、料理人の方がどう使ってくれたのかも知ることができます。この経験は本当にうれしくて、もうこのやり方はやめられないと思うようになりました。
今では、夏は礼文島で漁をして、冬は家族で昆布を届ける“昆布の旅”という生活が、僕たち家族の一年のリズムになっています。
-
「自然とともに生きる
─石原さんが語る礼文島漁師の魅力─」

石原さんにとって、漁師の魅力ややりがいについて教えてください。
僕にとって漁師のやりがいは、大自然の中で生きている実感を味わえることです。朝、海に出ると、海も空も山も全部が目の前に広がります。「自分って本当にちっぽけだな」と思うと同時に、海や島のおかげでウニや昆布を取らせてもらい、生かされているんだなと心から感じます。
また、自分の手で作ったものに愛情を込められることも漁師の魅力の一つだと思います。天日干しでこだわって作った昆布を、皆に食べてもらい「美味しかった」と言ってもらえると、「この仕事をやっていてよかったな」と心から思います。自然の中でのびのび働けて、自分の手で作ったものが人に喜ばれる。これが、僕にとって漁師の一番のやりがいです。
-
「自然の恵みに感謝しながら働くということ」
一方で漁師として大変と感じていることを教えてください。
漁師には、いくつか大変な面もあります。ひとつは、収入が安定しにくいことです。たくさん漁ができれば収入は増えますが、海の状況や季節、天候によって思うように漁ができない日もあります。
また、自然との戦いになることも避けられません。海の仕事は、風が強い日や波が高い日には危険をともないます。命の危険を感じる場面もあり、毎日のように早朝から作業が始まるため、体力も必要になります。
そして最近では、海の環境変化による影響も深刻です。近年は地球温暖化の影響で海水温が上昇し、礼文島の名産であるエゾバフンウニが大量に死んでしまうこともありました。海の資源が減ってしまえば、どれだけ努力しても漁ができなくなってしまいます。「海そのものが変わってしまうかもしれない」という不安は、漁師にとって最も大きな悩みです。
でも、こうした大変さがあるからこそ、自然の恵みに感謝しながら働く気持ちをいつも忘れないようにしています。
-
「後悔しないために今しかできない挑戦をしよう」

このインタビューを読んでいる学生にメッセージをお願いします。
中高生のみなさんに伝えたいのは、「今しかできないことが、ある」ということです。僕も、最初は障がい者施設で介護士として働いていましたが、「このままでいいのかな」と思い、自分の本当にやりたいことを考えました。
勇気を出して自転車一つで旅に出たあの経験が、今の自分――礼文島で漁師として生きている自分へとつながっています。もし、みなさんの中に「やってみたいけど、勇気が出ない」「失敗したらどうしよう」と思うことがあったら、思い切って一歩踏み出してみてください。やらないまま大人になると、きっと後悔すると思います。
そして、外の世界に出て、いろいろな景色や人に出会ってください。その経験は、いつか必ず自分の力になります。やりたいことがあるなら、今のうちに挑戦してみよう。その一歩が、未来の自分をつくると思います。
-
私のおすすめの1冊!
「一緒に旅した1冊、中高生におすすめしたい『旅をする木』とは?」
石原さんが中高生におすすめの本を紹介してください。
僕が中高生におすすめしたい本は、星野道夫さんの『旅をする木』です。この本は、僕が自転車で日本一周の旅をしていたとき、屋久島で出会ったお兄さんが「これ持っていけ」と手渡してくれました。旅の間ずっとリュックに入れていて、僕にとってはまるで“旅の仲間”のような本でした。『旅をする木』を読むと、日本や世界は本当に広いんだなと感じます。自分の知らない景色や、遠い場所で暮らしている人たちの生活を想像すると、「もっと外の世界を見てみたい」と思えてくるんです。
中高生のみなさんには、自分の生まれた町だけで人生を終わらせないでほしいと思います。本を通して旅をする気分を味わい、ときには実際に外の世界に出て、いろいろな景色や人に出会い、自分の世界を広げてみてください。
-
探究チャレンジ!
「未来の海や漁業を守るために、私たちにできることは何だろう?」
石原さんが、中高生に考えてほしい探究テーマを教えてください。
ー「考えてほしいこと」
「ここ数年、礼文島の海の水温が上がってきています。その影響で、海の生き物のすみかや数が変わってきました。たとえば、北海道では、今まで採れていなかったブリがとれるようになったり、逆に、温度に弱いエゾバフンウニが大量に死んでしまったりしています。普段の生活の中では、あまり意識することはないかもしれませんが、地球温暖化や海洋環境の悪化は、遠くの話ではなく、将来、食卓に並ぶ魚介類が減ることにつながります。
だからこそ、地球温暖化や海の環境の変化を「自分には関係ないこと」と思わずに、今できることを考えてほしいのと思います。ゴミを減らす、電気を大切に使う、そんな小さなことが、未来の海を守る力になると信じています。海の今と未来について、ぜひ考えてみてください。」
ー「基本知識」
「日本の海の平均水温は年々上昇しており、海の生き物のすみか(分布)が変化しています。また、地球温暖化や海洋環境の悪化は、海の生き物だけでなく、食や仕事にもつながる身近な問題です。」
↓↓ここからはワークシートとともに学習を進めていこう!!
ー「学習の進め方」
STEP1『探究テーマ』:
「未来の海や漁業を守るために、私たちにできることは何だろう?」
STEP2『原因の予想』:
「なぜ、海の生き物が減ったり、漁師の仕事に影響が出たりしているのか、原因を考えてみよう。(例:地球温暖化による水温上昇/海の汚れ/プラスチックごみの増加 など)」
STEP3『調べる』:
「地球温暖化や海の環境の変化について、どんな影響があるのか、どんな対策が行われているのかを調べてみよう。(例:エゾバフンウニの減少、ブリの北上、海洋プラスチック問題、漁師の声や取り組みなど)」
STEP4『解決方法を考える』:
「調べたこともとに、未来の海と漁業を守るために、どんな行動や取り組みができるか考えてみよう。(例:地元の魚を選んで食べるキャンペーンを企画する/ゴミ拾いやエコ活動を地域で広める/温暖化をテーマにしたポスターやSNS発信で多くの人に伝えるなど)」



-2.jpg)

.jpg)
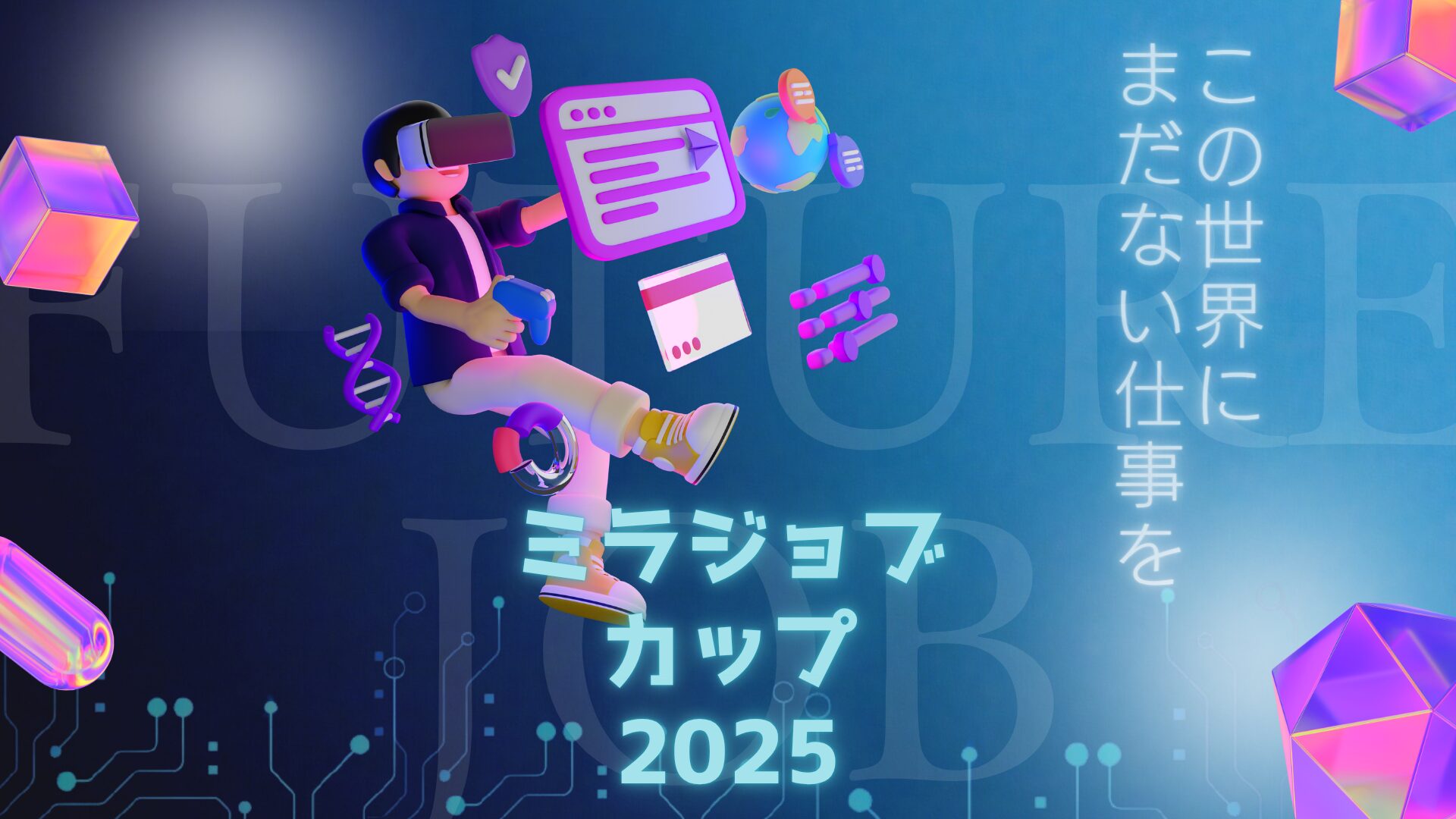
-2.png)
のコピー.jpg)
-1-1.png)
-1.jpg)
.jpg)
-3.jpg)
-600-x-397-px-1.png)
.jpg)
-2.png)
-3.jpg)
.png)
-2.png)
.png)
-1-1.png)
.jpg)
-2.png)
-2.png)
のコピー-1.png)
.png)
のコピー-4.jpg)
.jpg)
.png)
のコピー.png)
のコピー.jpg)
のコピー.png)
-1-1.png)
-1-1.png)
.png)
-1.png)
-2.png)
-1-1.png)
-4.png)
.png)
のコピーのコピー.png)
のコピー-1.png)
-1.png)
-3.png)
-2.png)
-1-1.png)
-1-1.png)
のコピー.png)
-1.png)
-600-x-397-px.png)
-1.png)
-1.png)
-3.png)
.jpg)
-1.png)
.jpg)
-1-1.png)
.jpg)
のコピー.png)
-1.jpg)
のコピー.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg.webp)
-4.jpg.webp)
のコピーのコピー-1.jpg.webp)
のコピー.jpg)
.jpg)








.png)

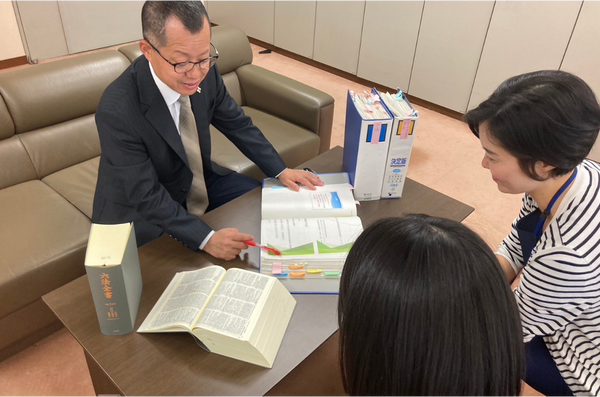
.jpg)







-1.jpg)
.png)

.png)

のコピー.jpg)
.png)
.png)
-1.jpg)
のコピー.png)
.png)
.png)
のコピー-1.jpg)
のコピー.png)
.png)
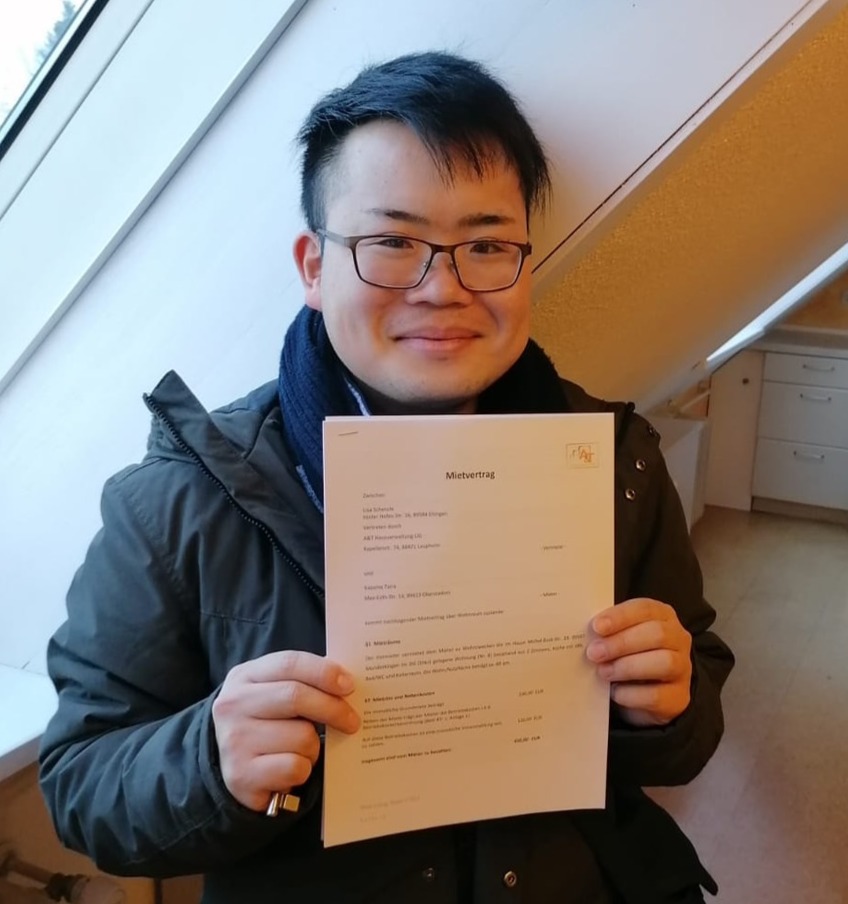
.png)
のコピー.png)
.jpg)
のコピー.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
-2.png)
.png)
.png)
のコピー-1.png)
.png)
のコピー-1-e1741854195145.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
のコピー-1.png)
.png)
-1.jpg)
.png)
.png)

.png)

.png)
のコピー.jpg)
.png)
のコピー.jpg)
のコピー.png)
-1.jpg)



.jpg.webp)
-1.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg)
のコピー-1.jpg)